近年、日本では在留外国人が増加しており、「多文化共生保育」や「多文化保育」という用語を見かけたことはないでしょうか。
ここでは、「多文化共生保育」「多文化保育」などの名称について解説します。
はじめに、異文化・多文化に関係する保育には多様な名称や定義があります
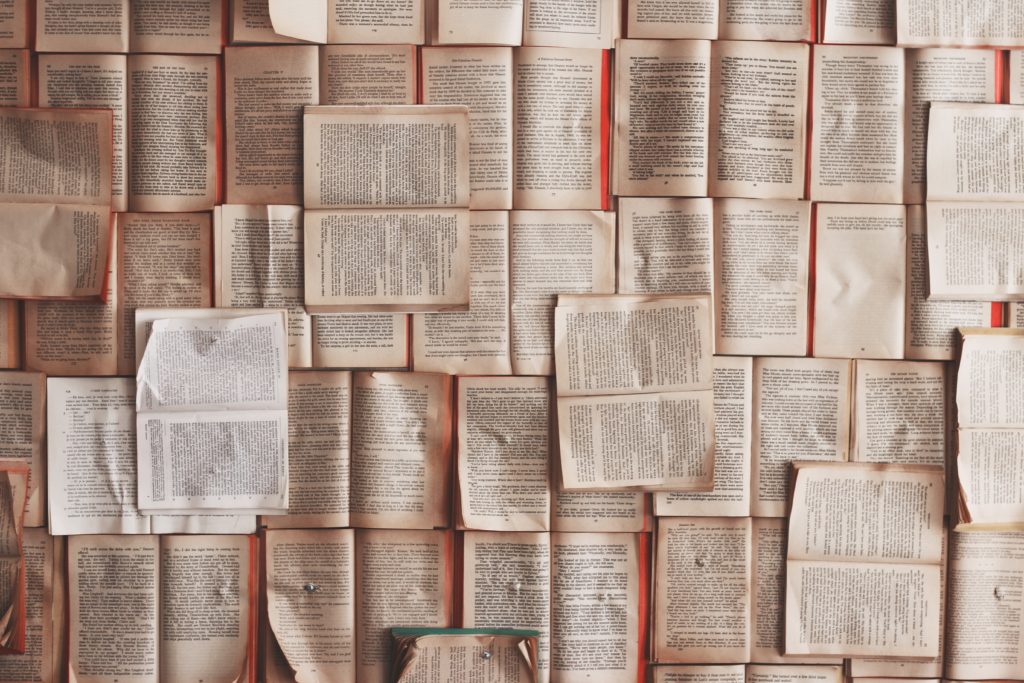
具体的に説明すると
- 多文化共生保育・多文化保育などの名称や定義はたくさんあり、日本では統一されたものはありません…
- 多文化共生保育・多文化保育の他にも「民族保育」や「異文化間教育」など様々な名称があります。
- ややこしいことに、同じ名称であっても実践者や研究者、保育所・幼稚園などの保育施設によって定義や捉え方に違いがあります。
しかし、全く異なるわけでもなく共通するところも多いです。
論文や資料などでよく見られる名称と、その定義を一部紹介すると、
●「多文化保育」では、
萩原(2008)が、「多文化保育論」の書籍で提唱したものがあります。
「『多文化保育』の概念は、地球市民の育成というグローバルな視点からニューカマー・オールドカマーを問わず、在日の日本語を母語としない幼児・保護者と日本人の幼児・保護者とが幼児の成長・発達の権利と原則を共有することの必要な視点、そして相互に理解し、学びあい、支援しあう、いわば幼児の視点からの統合性の意味を含んでいる」(萩原,2008)
|
|
●「多文化共生保育」では、
卜田(2012)が「日本における多文化共生保育研究の動向」の論文で提唱したものがあります。
「民族や国籍など様々な違いを認め会い、多文化という状況を共に生きるための力を育む保育」(卜田,2012)
また、「保育所保育指針」の解説では「多文化共生の保育」の表記が、
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の解説 では、「多文化共生の教育」の表記が記載されています。
 「多文化共生の保育/多文化共生の教育」省庁で使われる表記
「多文化共生の保育/多文化共生の教育」省庁で使われる表記
MEMO
- 多文化保育・多文化共生保育は、人種や民族の違いに留まらず、障がいや宗教、性差、LGBTなどの子どもの多様性について取り扱うことがあります。
- 名称(表記)の多様さについてもっと知りたい方は
卜田(2012)の「日本における多文化共生保育研究の動向」の論文にまとめられています。 - 多文化共生保育に関係する研究や発表をする際は、定義を論文や資料に記載することをオススメします。発表の場で定義について質問を受けることがあります。
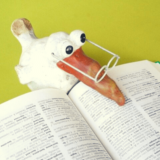 保育所保育指針から見る「多文化共生保育」
保育所保育指針から見る「多文化共生保育」
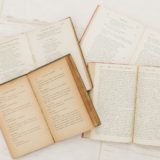 幼稚園教育要領から見る「多文化共生保育」
幼稚園教育要領から見る「多文化共生保育」
 幼保連携型認定こども園教育・保育要領から見る「多文化共生保育」
幼保連携型認定こども園教育・保育要領から見る「多文化共生保育」
 外国にルーツ持つ保護者・子どもの対応に役立つ「資料」
外国にルーツ持つ保護者・子どもの対応に役立つ「資料」
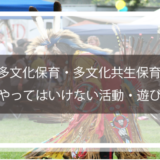 【注意】多文化保育でやってはいけない活動・遊び【ツーリストカリキュラム】
【注意】多文化保育でやってはいけない活動・遊び【ツーリストカリキュラム】
 子どもが人種の違いを気付くのはいつから?
子どもが人種の違いを気付くのはいつから?
引用文献
- 萩原元昭 (2008) 多文化保育論 学文社
- 厚生労働省 (2018) 保育所保育指針解説 株式会社フレーベル館
- 内閣府・文部科学省・厚生労働省 (2018) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 株式会社フレーベル館
- 卜田真一郎 (2012) 日本における多文化共生保育研究の動向 エデュケア 33 13-33


