 多文化共生保育・多文化保育ってなに?
多文化共生保育・多文化保育ってなに?
異文化・多文化に関係する保育には多様な名称や定義があります。
それでは日本の省庁では、どのような表記が使われているのでしょうか?
「保育所保育指針」の解説では「多文化共生の保育」の表記が、
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の解説 では、「多文化共生の教育」の表記が記載されています。
それぞれの記載箇所を説明すると
厚生労働省の保育所保育指針の「 4 保育の実施に関して留意すべき事項,(1)保育全般に関わる配慮事項」における「子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにすること。」の中に、以下のように記載されています
「保育士等はそれぞれの文化の多様性を尊重し、多文化共生の保育を進めていくことが求められる。」
内閣府の幼保連携型認定こども園教育・保育要領 の「第4 教育及び保育の実施に関わる項, 2幼保連携型認定こども園における教育及び保育の全般における配慮事項」における「園児の国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにすること。」の中に、以下のように記載されています
「保育教諭等はそれぞれの文化の多様性を尊重し、多文化共生の教育を進めていくことが求められる。」
多文化共生の保育の多文化共生の教育のどちらも表記は違えど同じ文章ですね。
多文化共生の保育と多文化共生の教育の記載箇所の解説も用語が異なるだけで大枠は同じ内容になっており、以下のようになっています。※内容が重複しているため、以下の( )の用語は保育所保育指針の用語を指す。
解説
「外国籍の保護者に自国の文化に関する話をしてもらったり、遊びや料理を紹介してもらったりするなど、教育及び保育において園児(子ども)や保護者が異なる文化に気付き、興味や関心を高めていくことができるよう、園児同士(子ども同士)の関わりを見守りながら、適切に援助していく。その際、外国籍の園児(子ども)の文化だけでなく、宗教や生活習慣など、どの家庭にもあるそれぞれの文化を尊重することが必要である。」
「保育教諭等(保育士等)は、自らの感性や価値観を振り返りながら、園児や家庭の多様性を十分に認識し、それらを積極的に認め、互いに尊重し合える雰囲気をつくり出すなとに努めることが求められる。」
内閣府・文部科学省・厚生労働省 (2018)
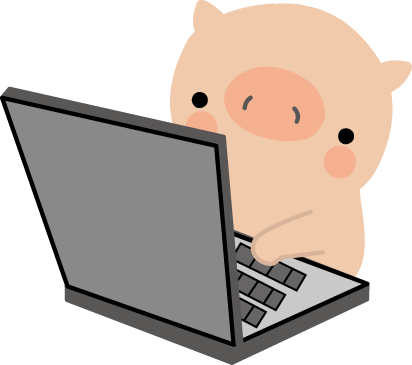 管理人
管理人
- 多文化共生の保育と多文化共生の教育の内容をまとめると、
異文化・多様性の理解や、子どもが異文化に気付き興味や関心を持つこと、異文化の尊重をねらいとした内容になっています。 - 省庁で使われている表記ではありますが、論文や保育施設では、それぞれ独自の表記が使われています。
- 厚生労働省 (2018) 保育所保育指針
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf (2020年1月26日閲覧) - 厚生労働省 (2018) 保育所保育指針解説 株式会社フレーベル館
- 内閣府・文部科学省・厚生労働省 (2018) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/seisyourei/h260430/c1-2-honbun.pdf (2020年1月26日閲覧)
- 内閣府・文部科学省・厚生労働省 (2018) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説 株式会社フレーベル館


