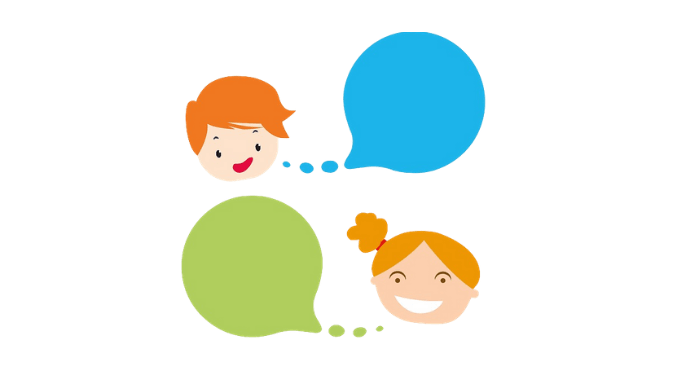多文化共生保育の論文や資料をみると「外国の子ども」、「外国にルーツを持つ子ども」、「日本語を話さない子ども」など様々な呼称(呼び方)を見たことがあると思います。
子ども一人一人によって、国籍や文化、生まれ育った場所、家庭で話す言葉、親の国籍、日本での滞在歴などは異なり、一括りはできないですよね。
➡︎ そのため様々な呼称が使われています。

卜田(2012)は、先行研究で取り扱っていた呼称には「国籍」、「言葉」、「文化」、「対象が1つのエスニシティに限定されているもの」の4つの分類に分けられていることを指摘しています。
例えば
「外国籍の子ども」(内田,2013)
「日本語を母語としない子ども」、「日本語非母語児」(廿日出,1999)
「多文化の子ども」(宮崎,2014)
「中国人幼児」(柴山,2002)、「ブラジル人児童」(品川,2011)
※エスニシティとは共通の出自・慣習・言語・地域・宗教・身体特徴などによって個人が特定の集団に帰属していること。
名称(表記)の多様さについてもっと知りたい方は卜田(2012)の「日本における多文化共生保育研究の動向」の論文によくまとめられています。
加えて、これらの分類の複数の要素が入った定義もあり、広義的な呼称も使われています。

日本で暮らす 複数の文化背景をもつ子どもたちであり、以下のいずれかに該当する。
- 本人が外国籍の場合
- 本人が日本国籍で、 保護者(両方または一方) が外国籍の場合
- 本人も保護者も日本国籍であるが、 本人または 保護者(両方または一方)が外国語を母語としている場合
研究や資料などを作成される場合は、保育の名称(表記)と同様に、定義を記載したり先行研究から引用されるのが良いと思います。
本ブログで使用する呼称も紹介します。
「外国にルーツを持つ子ども」
「外国にルーツを持つ子ども」とは、一般的には「父・母の両方、またはそのどちら一方が 外国出身者である子ども」とされる。この定義では、在留外国人の子息を含めて、日本国籍を含む重国籍の子どもや海外で生まれ育った日本国籍の子ども(帰国子女)、無国籍の子ども、生活言語が日本語ではない子どもなど、その範囲は広がっている(森,2018)。
|
|
- 廿日出里美 (1999) 保育所における異文化間の友達関係の凝視的分析 保育学研究 37 (1) 43-50
- 平野知見・鈴木祥子・竹下秀子 (2012) 「多文化な子ども」 の 「気になる姿」 は保育園所でどう捉えられているか-滋賀県内保育園所を対象とした多文保育の実態調査から 人間文化 滋賀県立大学人間文化学部研究報告 32 52-59
- 宮崎幸江 (2014) 多文化の子どもの家庭における言語使用と言語意識. 上智大学短期大学部紀要』(34) , 117-135
- 森雄二郎 (2018) 外国にルーツを持つ子どもと社会をつなぐ場の創出に関する実証研究: 社会構成主義的アプローチを用いた教育実践を通じて 同志社政策科学研究19(2) 169-184
- 柴山真琴 (2001) 幼児の異文化適応過程に関する考察:中国人5歳児の保育園への参加過程の関係的分析 日本幼児教育学会誌 幼稚園教育学研究 11 69-80
- 卜田真一郎 (2012) 日本における多文化共生保育研究の動向 エデュケア 33 13-33
- 品川ひろみ (2011) 多文化保育における保育者の意識. 現代社会学研究 24, 23-42
- 鈴木祥子・平野知見・竹下秀子 (2013) 就学前保育における日本語指導と母語指導: 滋賀県内保育園所を対象とした多文化保育の実態調査から 人間文化 滋賀県立大学人間文化学部研究報告 33 18-25
- 内田千春 (2013) 新人保育者の語りに見る外国につながりのある子どものいる保育 共栄大学研究論集 (11) 273-27