「多文化共生保育・多文化保育ってなに?」の記事で解説したように、多文化共生保育・多文化保育では様々な名称(表記)と定義が使われています。
ここでは、日本の先行研究や幼稚園・保育所などの保育施設で、様々な名称(表記)と定義がある理由について、解説します。

先行研究では
卜田(2012)は「様々な表記があり、その意味する内容や問題意識に違いがある」ことを指摘しています。
つまり、卜田(2012)は、どのような表記を用いるのかということが、
その研究調査における「誰を対象にするのか」、「どのような問題を対象にするのか」という判断と関連しており、
その判断自体に研究者自身の課題の捉え方、社会的・歴史的文脈の捉え方が反映されている可能性を指摘しています。

保育施設では
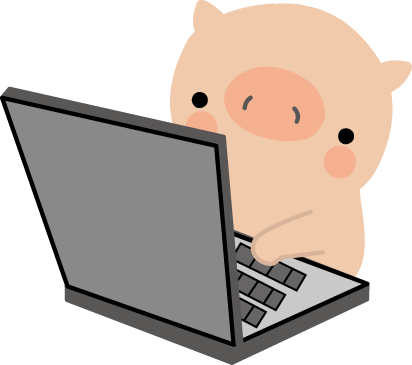 管理人
管理人
管理人が多文化共生保育・多文化保育を行っている幼稚園や保育所から
お話を伺って思ったのですが、
保育施設では、課題の捉え方、社会的・歴史的文脈の捉え方に加えて、
その保育施設の教育理念や時代背景、地域の特徴、保育施設によっては宗教が関係していると思いました。
まとめ
日本の先行研究や幼稚園・保育所などの保育施設で、様々な名称(表記)と定義がある理由として、
先行研究の場合は
研究者によって、課題の捉え方と社会的・歴史的文脈の捉え方が異なるためだと指摘されています(卜田,2012)。
保育施設の場合は
保育施設ごとに、それぞれの教育理念や時代背景、地域の特徴、宗教などが影響しているため、様々な名称(表記)や定義があると思われます。
|
|
引用文献
卜田真一郎 (2012) 日本における多文化共生保育研究の動向 エデュケア 33 13-33




